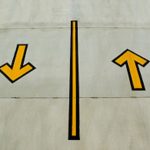チェーホフをきちんと読んだのは、本書が初めて。
収められている13編は、味わいのある佳作ばかりです。
中でも、10番目の掌編『せつない』は、福祉専門職として考えさせられる、印象深い物語でした。
主人公は、年老いた御者のイオーナ。夕暮れ時、雪にまみれながら辻橇(そり)を走らせています。
イオーナは先日、息子を病気で亡くしたばかり。街角で客を乗せては、死んだ息子のことを話そうとします。
けれど、橇の乗客たちは、誰も耳を傾けてはくれません。
受容と傾聴、そして共感
「若い男が水を飲みたいのと同様に、彼は話がしたくてたまらない。息子が死んでからもうすぐ一週間になるというのに、まだ彼は誰ともきちんと話していないのだ…。筋道だてて、じっくり話さなければならない…。どんな風に息子が病に倒れ、どんなに苦しみ、死の間際に何を言ったか、どんな風に死んだか、話さなければ…。(中略)それを聞いた誰でも嘆き、溜息をつき、泣いてくれるに違いない…。」
宿に戻ったイオーナは結局、厩(うまや)の愛馬に、せつない胸の内を語るのでした。
イオーナが求めていたのは、受容と傾聴、そして共感です。
かつて相談支援の基礎として学んだ、それらの大切さを、改めて教えられたような気がします。
帝政時代のロシアであっても、現代の日本であっても、つらく苦しい立場にある人びとに必要とされるものは、同じなのでしょう。

![新訳 チェーホフ短篇集 [ アントン・チェーホフ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4706/9784087734706_1_2.jpg?_ex=128x128)