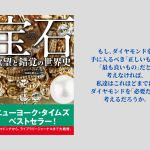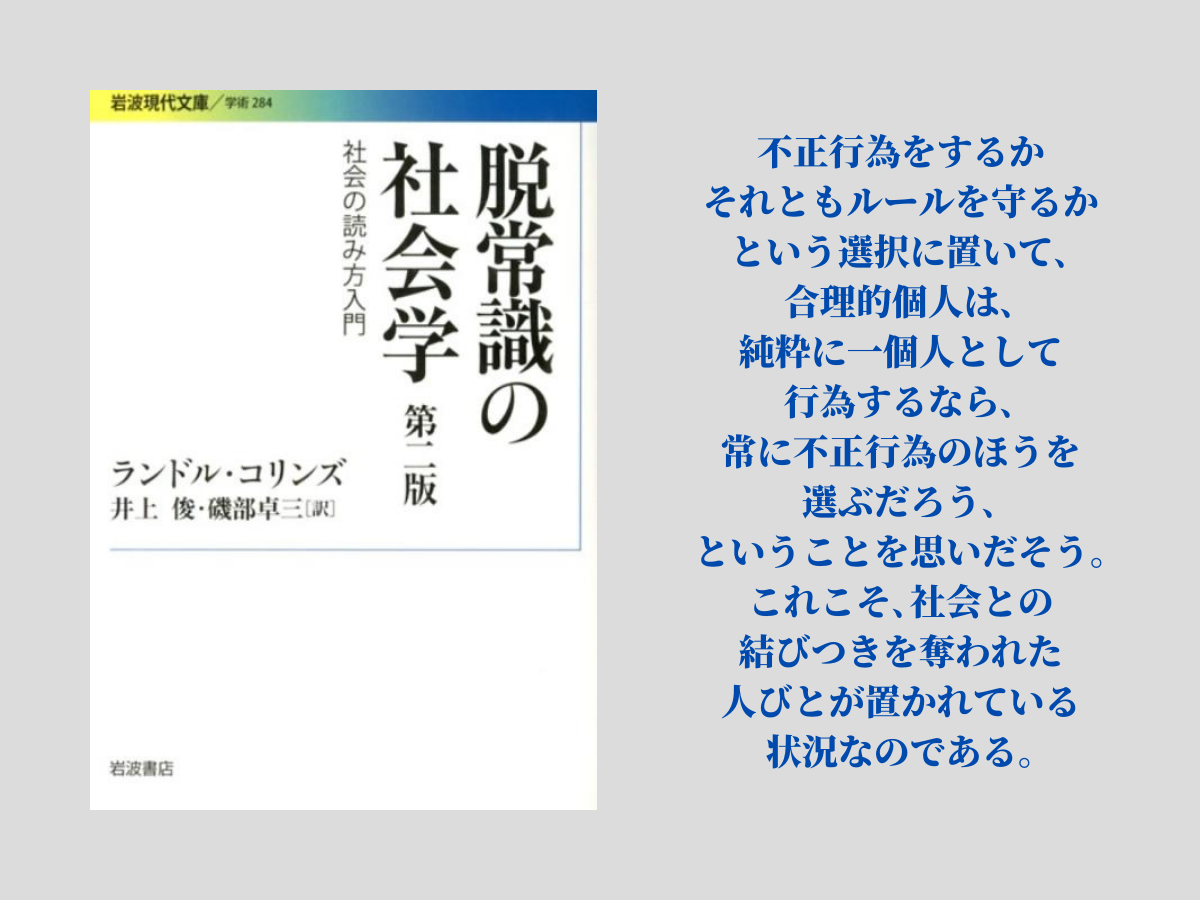
約束や宗教や政治や犯罪や結婚などなど、私たちが日常的に関与してるさまざまなモノゴトについての“常識”を、社会学でもってバラバラに解体してみせる本。
例えば宗教。
神社で柏手を打つとか、教会で十字を切るとか、そんな非日常的で不合理な行為が求められるのは、儀礼そのものに宗教の本質があるから。
儀礼に頼らない宗教なんて、よくよく考えてみれば、確かに無理っぽい。実は神様の有無なんか、宗教にとって大した問題じゃないのかも知れない。
例えば犯罪。
刑罰を厳しくしても、犯罪はなかなか減らない。けれど、貧困や差別などを解消したところで、減少に転じるものでもないらしい。
この社会が営まれる過程で、必然的に生じてしまうのが犯罪。もはや社会システムの一部とも言え、警察力や法制度で抑制するには限界があるそうな。
古今の碩学たちの理論や統計などに基づいて書かれてる本書は、だからこそ説得力があってエキサイティング。その半面、シビアすぎて身も蓋もないカンジも。
表彰式とか葬儀とか祝賀会とか、それらの背後に“仕掛け”の存在を疑うようになってしまうと、もう素直に感動したりできなくなりそうだぞ。
恐るべし社会学。
最終章「社会学は人工知能をつくれるか?」は、知見としては陳腐化してる模様。むしろ、ちょっぴりホッとしましたw
![脱常識の社会学 社会の読み方入門 (岩波現代文庫 学術284) [ ランドル・コリンズ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2848/9784006002848.jpg?_ex=128x128)