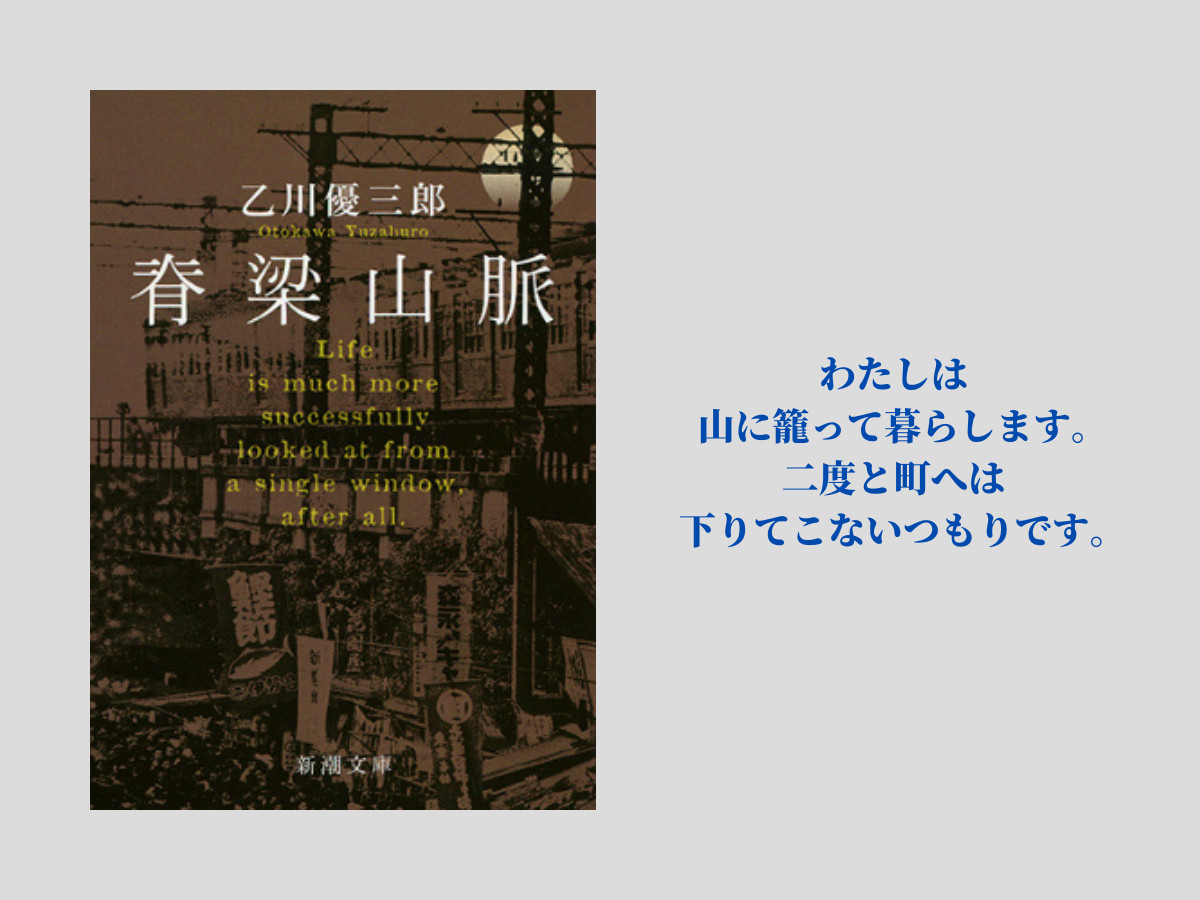
乙川優三郎の長編小説。
終戦直後の日本が舞台。
主人公は上海からの復員兵で、たまたま窮地を救ってもらって別れた青年が、木地師らしいと知る。
木地師とは木工の職業集団。9世紀ごろの滋賀県・近江発祥とされ、良材を求めて各地を流浪してたそうな。
恩ある青年の行方を訊ねる過程で、木地師の歴史に興味を抱くようになる主人公。痕跡を求めて山奥へ分け入ったり、古代史の謎に切り込んだり。
敗戦による喪失感を埋めるかのような行動だけど、人生をリセットすることができず、木地師の図録作りに打ち込むばかり。
ところがどっこい。
この主人公ときたら、企業経営者だった伯父が病死して、少なくない遺産が転がり込み、働かずに暮らせる高等遊民に。しかも、自由奔放な画家のツンデレ美女と、奥ゆかしい芸者のしっとり美女と、二股かけやがるし。
ウジウジ苦悩しようが何だろうが、客観的には“リア充”だぞ。
著者は文章が実に流麗。主人公の心象にシンクロしてるような戦後日本の風景とか、人間模様の繊細な描写とか、皇統をめぐる推理とか、木地師の盛衰とか、読みどころもたくさん。
なのに、主人公へのうらやましさに目がくらんでしまったのでしたw


