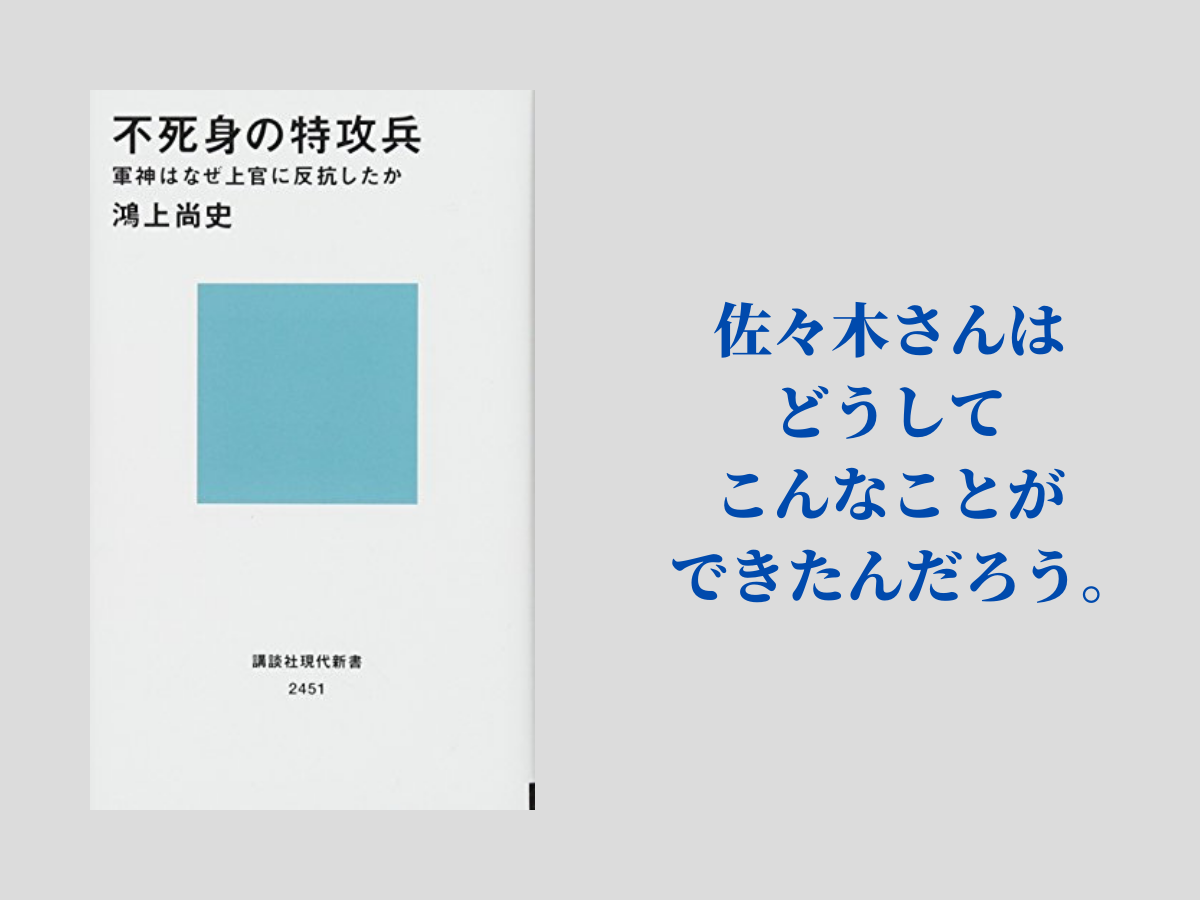
劇作家の鴻上尚史によるルポルタージュ。
第二次大戦末期、日本陸軍の特攻兵として爆撃機で9回出撃し、生還したパイロットがいた。
そのことに興味を抱いてた著者が、当人が存命と知って所在を探し当て、インタビューに臨んだ意欲作。
この人物は「体当たりをしないで、戦艦を沈めるにこしたことはない」という気概と技能の持ち主。実際に戦果も挙げたという。
それでも、「やっぱり無駄死にはしたくなかった」との言葉には、無謀な命令に従わざるを得なかった当事者としての深刻さ、重みが感じられる。
書名から想起されるような“痛快”な内容では、決してない。
本書の後半では、さまざまな文献を調べた著者が、特攻という戦術の理不尽さや、精神論に傾倒した軍首脳の無能ぶり、特攻隊の戦死者を“軍神”に仕立てたマスコミの姿勢などを、厳しく糾弾してる。
特攻については「戦術として有効で、米軍に大きな損害を与えた」とする見解もあるらしい。
けれど、兵士に爆死を強いらなきゃならないところまで追い詰められてる時点で、もはや軍隊として“ダメ”でしかないし、戦争として“負け”でしかないと思う。
特攻兵にまつわる「みんな穏やかに笑い、祖国を守ろうと進んで出撃した」的さわやかなイメージは、特攻を命じた側である上官たちの証言に基づき、戦後に形成されたそうな。
若くして死んだ特攻兵を賛美することで、生き延びた上官たちの行為が正当化される…そんな構図を、著者は指摘する。
これって戦時中に限ったことじゃないぞ。
権力者が誰かを賛美する時、そこに“後ろめたさ”とか“ちゃっかり便乗”みたいな思惑が透けて見えること、今だってありますよね。
よくよく警戒しなきゃ…。
![不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗したか (講談社現代新書) [ 鴻上 尚史 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4518/9784062884518_1_2.jpg?_ex=128x128)

