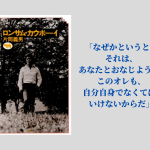以前に書いた「私たちが受け取っているもの」において、「視覚障害のある人に、美術館で絵画について説明し、鑑賞を支援する」という活動に触れました。
障害者への支援とは、実は双方向の行為かもしれない…との認識をもたらした、ひとつの例として挙げられたものです。
まさにその活動自体を紹介しているのが本書。
視覚障害者の美術鑑賞を著者がアテンドした体験記です。
白鳥さんは全盲の50代男性。たまたま若いころに美術館を訪れたことをきっかけに、美術鑑賞を楽しむようになりました。
美術館に電話をかけ、そこの職員に案内を依頼。戸惑われたり断られたりしても粘り強く交渉し、鑑賞を果たしてきたそうです。全盲の美術鑑賞者としてはパイオニア的存在かもしれません。
美術鑑賞のアテンドでは、目の前の美術品(絵画や造形物、インスタレーションなど)について、白鳥さんに言葉で説明することになります。
作品の大きさ、表現されているもの、受ける印象など、著者は「何が見えるか」「どう見えるか」を、そばに立っている白鳥さんに語ります。
白鳥さんへのアテンドから、著者は多くの気付きを得ます。
一人で鑑賞する時よりも、美術品への集中が深まること。見たものを言葉で表現することの難しさ。鑑賞する際の気分や姿勢や環境。複数人でアテンドした時には、同じ美術品を鑑賞しながらも、受ける印象が自分と他人で大きく異なることに驚いたそうです。
支援から受け取れるものの大きさ
アテンドする著者らの説明に耳を傾け、白鳥さんは“鑑賞”します。
「俺にとっては、みんなで見る、話すというプロセスの中で意味を探ったり、発見していくのが面白い」と白鳥さん。著者は「どうやら彼は、作品に関する正しい知識やオフィシャルな解説は求めておらず、『目の前にあるもの』という限られた情報の中で行われる筋書きのない会話にこそ興味があるようだった」と書いています。
視覚障害者はアテンドによって美術鑑賞が果たせます。一方、アテンドする側は、アテンドという行為によって“感度”が向上し、より深い鑑賞体験が得られるのです。
互いに支援し、支援される…双方向の行為によって、そこに豊かな時間が現出していることが分かります。
本書において著者は、障害のある人たちによる美術作品を見に行ったり、鑑賞者に夢を見てもらうという体験型の作品のために宿泊旅行に出るなど、白石さんとさまざまな美術鑑賞を実施。と同時に、障害者差別や郵政思想、自己責任論などの社会問題へ、興味や関心を拡げていきます。
支援という行為から受け取れるものの大きさを教えてくれる一冊です。
![目の見えない白鳥さんとアートを見にいく [ 川内 有緒 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3999/9784797673999_1_5.jpg?_ex=128x128)